お世話になった人や大切な人に贈り物をする恒例行事、日本では年に2回、お中元とお歳暮がありますよね。
そこで今回は、お中元の時期2023年はいつからいつまでなのか、具体的にお伝えしたいと思います。
お中元の時期2023年について以外に、他にもいろいろリサーチしてみました。
お中元のマナーや、お中元の時期を過ぎたらどうすればいいのかも、レクチャーしますので、ぜひ最後までご覧ください。
- お中元の時期2023年はいつからいつまでなのか
- お中元のマナーで注意すること
お中元の時期2023年はいつからいつまで?
 お中元の時期2023年はいつからいつまでなんでしょうか?
お中元の時期2023年はいつからいつまでなんでしょうか?
実は、お中元は地域によって贈る時期が違うので、注意する必要があります。
お中元の時期2023年の場合、下記を参考にして、贈る相手が住んでいる地域に合わせるようにしましょう。
- 北海道:7月15日~8月15日
- 東北・関東・北陸:7月1日~7月15日
- 東海・関西・四国・中国:7月15日~8月15日
- 九州:8月1日~8月15日
- 沖縄:8月10日~8月12日
7月初旬~8月初旬:お中元
日ごろからお世話になっている人たちに対して感謝の気持ちを伝えるために贈り物をする風習があります。時期は地域によって変わりますが、概ね7月初旬~8月初旬までの間に贈り物をします。お中元は様々なマナーがあるので、贈る際には一度マナーを確認すると良いでしょう。— ぎょうじちゃん (@sachasachayo) May 4, 2022
しかし最近は早割でお得になったり、人気商品は品切れになることがあるので、早めに贈る風潮があるようです。
全国的に6月下旬から7月15日に届くのが一般的になっていますが、地域別の日にちより早めに届くのは問題ありません。
なぜ、地域によってお中元の時期2023年が違うかというと、お盆の時期が地域によって異なるからです。
関東地方の場合は7月15日あたり、関西地方では旧暦のお盆である8月15日あたりが多いみたい。
沖縄は特殊で、旧暦の7月13日から7月15日までのお盆(新暦では2023年は8月10日から8月12日)にお中元を贈る風習があるそうです。
そもそもお中元とは、日頃お世話になっている人に対して、感謝の気持ちを込めて贈り物をする習慣のこと。
お中元の起源は、旧暦の7月15日に行われていた道教の行事で、先祖の霊を供養する日でした。
それが江戸時代以降に、お盆のお礼としてお世話になった人たちに贈り物をする、今のような形になったと言われています。
ということで、お中元の時期2023年はいつからいつまでと一概には言えませんが…
新盆が主流の関東地方ではお中元も7月15日頃、旧盆が主流の関西地方では8月15日頃にお中元を贈ることが多いようです。
お中元の時期2023年は、相手の住んでいる地域に合わせて、お中元を贈るようにしてはいかがでしょうか。
お中元のマナーで注意すること
 お中元は相手に対する日頃の感謝の気持ちなので、相手のことを考えて贈ることが大切です。
お中元は相手に対する日頃の感謝の気持ちなので、相手のことを考えて贈ることが大切です。
ここからは、お中元のマナーで注意することを、具体的に見ていきたいと思います。
お中元のマナーで注意すること①相手の家族構成や好みをリサーチする
相手の家族構成や好みを事前にリサーチしておけば、より喜ばれることでしょう。
逆に嫌いな物を贈ってしまうと、嫌がらせにもなりかねないので、日頃のコミュニケーションが大事ですよ。
相手の好物だからといって、毎年同じ物を贈るのも、心がこもっていないように思われるので、気をつけたいところ。
お中元のマナーで注意すること②贈る日時を配慮する
贈る相手の生活環境が分かる場合は、贈る日時にも配慮するといいでしょう。
働いていて昼間に家人がいない場合は、平日の夜や土日に時間指定するなど。
もし、毎年贈っているなら、事前に希望日時を確認するといいかもしれませんね。
仕事上の付き合いで贈る場合、会社によってはお中元のやりとりが禁止されている場合があるので、事前に確認することをおすすめします。
お中元のマナーで注意すること③水引は蝶結び
日本では贈答品やお祝儀に、水引と呼ばれる帯紐を使うのが一般的です。
お中元の場合は、これからも良い関係性を続けたいという意味をこめて、紅白の蝶結びを選びます。
ちなみに、水引の意味として、蝶結びは何度あっても良いことに使われ、例えば出産祝いや入学祝いなど。
結び切りは一度きりで終わらせたいこと、例えば結婚祝いや快気祝いなどに使われます。
4月から制作していた出産祝いの記事を、いよいよ明日公開できそうです!
記事では、出産祝いで知っておきたいマナーも紹介しています。
本日はそのマナーの中から、熨斗(のし)に関するクイズを出題します✨
正解は明日、こちらのツイートにリプするので、もしよかったら挑戦してみてください☺️ pic.twitter.com/nDlN7EHrUD— カミムラナナ@素敵なギフトのなかのひと (@kamimura_nana) June 2, 2020
最近では、熨斗(のし)に水引が印刷された掛け紙で包装することが多いようですね。
ということで、お中元のマナーで注意することについて、お分かりいただけたでしょうか?
せっかく贈っても、お中元のマナーがきちんとしていないと良くない印象が残ってしまうので、以上のことは気をつけたいものですね。
お中元の時期を過ぎたらどうすればいい?
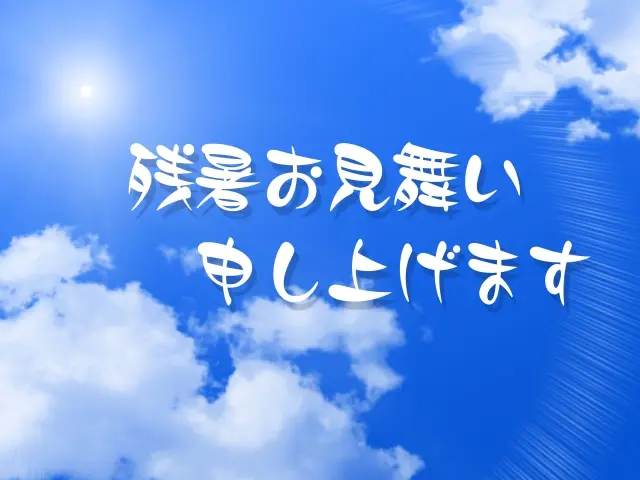 もし、お中元の時期を過ぎたら、どうすればいいのでしょうか?
もし、お中元の時期を過ぎたら、どうすればいいのでしょうか?
贈る品物は同じでも構いませんが、表書きを変える必要があります。
立秋(2022年は8月8日)までは『暑中御見舞』、それ以降は『残暑御見舞』と書くようにしましょう。
贈り先が目上の場合は、立秋までは『暑中御伺い』『残暑御伺い』、それ以降は『残暑御見舞』『残暑御伺い』とします。
「中旬過ぎたからお中元じゃなくて暑中御伺ね~」と娘が買ってきたヨックモックのアイス🍨
普通のシガールより一回り太くて意外とサッパリ😋💕 pic.twitter.com/sR2t33C3fp— あつやき (@Raggedtiger_Mmy) July 19, 2019
お中元の時期を過ぎたら、慌てずすぐに贈ることが大事ですが、遅くとも8月末までには届くようにしましょう。
お中元の時期2023年はいつからいつまで?マナーや注意点なども解説!:まとめ
お中元の時期2023年はいつからいつまでか、お分かりいただけたでしょうか?
お盆とお中元には深い関係があり、新盆の関東では7月15日頃、旧盆の関西では8月15日頃にお中元を贈る習慣があります。
お中元を贈る相手が住んでいる地域に合わせて、贈る時期も気をつけるようにしたいものですね。
お中元のマナーで注意することは、家族構成や好みを考慮して贈答品を選ぶ、贈る日時に配慮する、水引は蝶結びを選ぶなど。
もしお中元の時期を過ぎたら、熨斗の表書きを『暑中御見舞』『残暑御見舞』などに変えてくださいね。
普段なかなか伝えられない感謝の気持ちをこめて、大切な人たちに今年はお中元を贈ってみませんか?

